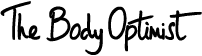電気を消す前に、親はベッドの下を覗き込み、子供部屋をざっと調べて安心させます。多くの子供たちは、マットレスの裏側にモンスターが隠れていると信じています。そして、子供たちの描写から判断すると、それはピクサー映画のような親しみやすいモンスターではなく、邪悪な生き物です。モンスターはホラー映画にしか存在しないと思っているかもしれませんが、これは見た目よりもはるかに深い比喩なのです。
正常で健全で必要な恐怖
誰もが聞いたことがあるでしょう。時にはささやき、時には叫び声のように、いつも同じ切迫感を込めて。 「ベッドの下に怪物がいる!」この言葉は、世代を超えて普遍的な子供時代の通過儀礼のように受け継がれています。そして親は、「ゴーストバスターズ」の登場人物のように、部屋の隅々まで確認せずにはいられません。子供に何も恐れることはなく、安全であることを証明するために、部屋全体をひっくり返します。最初は親は「それは全部子供の思い込みで、そのうち治まる」と自分に言い聞かせますが、それは全くの間違いではありません。4歳か5歳頃になると、子供たちは無限の想像力を発達させます。彼らの脳はまさにシナリオ生成器となり、影を生き生きとさせたり、不思議な音を出して本当に恐ろしいと思わせることができるようになります。
この年齢になると、脳は未知のもの、暗闇、そして部屋に親がいない状況に対処することを学びます。一見不合理な恐怖のように見えるものも、実は感情学習の段階です。子どもは自分の限界を試し、不安を探求し、それを制御する方法を見つけます。言い換えれば、ベッドの下の怪物は役に立つ存在です。深いところに飛び込む前に泳ぎ方を学ぶように、子どもの恐怖を鎮めるのに役立つのです。
それは生存本能が語っているのです。
ベッドの下に怪物が隠れていると信じているこの子は、怖い話を聞いているわけではありません。ただ、夜に対する普通の反応をしているだけです。先史時代から、私たちの脳は暗い場所、聞き慣れない音、隠れた空間に自動的に反応してきました。私たちの祖先にとって、危険は岩の後ろ、茂みの中、あるいは隠れ家の下に潜んでいる可能性がありました。この生物学的プログラムは今日でも活発に機能しており、特に感情を司る脳が非常に優位な幼い子供たちにおいては顕著です。
その結果、ベッドの下は暗く、近づきがたく、見慣れない場所となり、まさに警戒反射を誘発する場所となります。子どもの脳はそこを潜在的に危険な場所と認識し、想像力がそれを怪物、生き物、あるいは「何か」といった形で表現します。畳の上で寝ている子どもは、おそらくこのような恐怖を抱かないでしょう。
モンスターが感情を表現するとき
ベッドの下の怪物、つまり想像上の友達の敵役は、 子どもの恐怖を擬人化した存在です。言い換えれば、子どもの眠りを遅らせ、影に隠れているこの怪物は、様々な感情の集合体です。夜になると子どもたちの心に忍び寄るこれらの小さな生き物は、次のようなことを象徴しているのかもしれません。
- 最近の心配事(別居、引っ越し、進学)
- 彼はまだその感情をどう名付けるか知らない。
- 安心させられること、抑制されること、耳を傾けられること、
- あるいは単に壮大な物語を通して存在する必要性だけかもしれません。
実際には、モンスターは表現の媒体として機能します。漠然とした感情が突如として具体的になり、視覚化され、安心感を与えます。モンスターについて語り、対峙し、追い払うことができるのです。だからこそ、怯えた子どもに「モンスターなんて存在しない」と説得するよりも、話を聞いてあげる方が効果的な場合が多いのです。子どもにモンスターを言葉で表現したり、想像したり、描いたり、名前を付けたりさせることで、子どもの脳はコントロールを取り戻すためのツールを得られるのです。
ベッドの下のモンスターは消えるのではなく、より大きな内なる強さへと道を譲ります。お子さんがその存在を恐れるのではなく、受け入れるようになるには、「モンスターズ・インク」を見せてあげましょう。きっと、観終わった後にモンスターにおやすみなさいを言うのが楽しくなるでしょう。