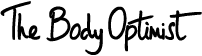デジタル時代において、母親たちはあらゆる角度から赤ちゃんを捉え、あらゆる瞬間を即興の写真撮影に変えています。しかし、家族写真では母親はレンズの奥に隠れたまま、姿を現さないことがよくあります。ヴィクトリア朝時代、写真撮影は忍耐力の試練であり、1ミリ秒をはるかに超える時間を要しました。母親たちは背景に浮かんでいました。物理的には存在していたものの、視覚的には不在で、幽霊のようにシーツに覆われていました。ティム・バートンの映画にもふさわしいこれらのポートレートは、200年経った今でも人々の心を魅了し続けています。
シーツの下に隠れた母親たち
これらの古びた肖像画は、血の気が凍るような感覚を覚える。時の痕跡を刻み込み、何よりも、見る者の心にある種の不安を呼び起こす。まるで超常現象を生き延びてきたかのようだ。しかし、これらはヴィクトリア朝時代に撮影された、ゆりかごから出たばかりの乳児のスナップショットに過ぎない。ただ、不穏なディテールが散りばめられており、見る者は何度も目をこすりたくなるほどだ。籐の籠や綿のガーゼのシーツに包まれた乳児を写す現代のプロの写真とは異なり、これらの写真には非定型の装飾的な要素が見られる。まるで幽霊のような存在感だ。
子供たちの背後には母親たちのシルエットがはっきりと映り、まるで生きた装飾品のようだ。母親らしき人々は、繊細さなど微塵もない布に包まれている。まるでカメラと隠れんぼをしながら、見つからないように用心しているようだ。写真の主題である子供たちは、カーテンに覆われた見えない膝の上に座ったり、布でできた腕に抱きしめられたりしている。どこからともなく現れた手は、まるで彷徨う精霊のような錯覚を抱かせ、ベルベットの長椅子からは女性の顔が白衣の貴婦人のように突き出ている。
母親をあからさまに描き、主人公として描く現代の写真とは異なり、ヴィクトリア朝時代の子供たちの肖像画では、母親は背景に位置づけられている。母親をコートの下に隠し、単なる物に貶めることは、残酷、あるいは病的な印象を与えるかもしれない。しかし、これは母親を抑圧したいという純粋な意図というよりも、むしろ陽動作戦であった。
この投稿をInstagramで見る
赤ちゃんを落ち着かせるテクニック
現代では、シャッターを押すだけで、心温まる瞬間を捉え、子供たちの軌跡を辿ることができます。ビクトリア朝時代には、家族はカメラの祖先であるダゲレオタイプに頼らざるを得ませんでした。ダゲレオタイプは、家族の歴史を形ある記録として残し、光沢のある紙に赤ちゃんの顔を永遠に残すための道具でした。この装置は、現在私たちのポケットに収まっているポラロイドやスマートフォンよりもはるかに大きく、扱いにくいものでした。30秒から数分と、より長い露出時間を必要としました。
そのため、機転を利かせ、利用可能なものでやりくりする必要がありました。物理的な空間に閉じ込められ、カメレオンのように動き回る母親たちは、この間ずっと赤ちゃんをじっと動かさないように、かけがえのない精神的な支えとなりました。彼女たちは写真撮影を司り、当時の美的規範に定められた通り、実際には参加することなく、スムーズな進行を促しました。
ナグラーの理論によれば、母親たちが写真にはっきりと写るのではなく、カモフラージュポーズをとったのは、必要に迫られたからではなく、自らの選択によるものだという。「母親たちは、自分たちと子どもの間にではなく、子どもと見る人の間に親密なつながりを築こうとしたようだ」とテレグラフ紙の記事は述べている。
今でも、母親が写真に写ることは稀です。
ヴィクトリア朝時代の子供たちのポートレートが母親の存在を覆い隠し、その役割を静かに抑圧している一方で、私たちの個人的なアルバムを飾る写真も、それ以上に多くのことを明らかにしているとは言えません。これらの記念写真集をざっと眺めるだけで、そのことがよく分かります。母親は光沢のあるページの間にちらりと姿を現しますが、しばしば影に隠れ、フレームの外に隠れています。自撮り棒やコンパクトな三脚が普及した時代でさえ、母親は結局、この「ワン、ツー、スリー、スマイル」という決まりきったシーンから除外されてしまうのです。
児童文学専門の司書、ローラ・ヴァレット氏は、この症状とも言える失踪を記録した。どのように?それは自身の経験に基づいている。「私が整理した450枚の写真を見ると、夫が子供たちと一緒に写っているのは私より2倍多い」と、彼女はXに投稿した記事で嘆いている。彼女の観察とは?まるで彼女は家族生活のエキストラのようだが、実際には彼女は家族に全身全霊を注ぎ、あらゆるエネルギーを注ぎ込んでいるのだ。
アーカイブから発掘され、美術館に展示されているこれらのビクトリア朝時代の写真は、女性を軽視する残念な傾向を如実に物語っています。しかし、現代の技術にもかかわらず、母親たちは顔に閃光を浴びる感覚をあまりにも少なくしか経験していません。